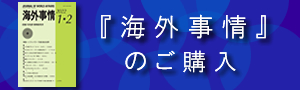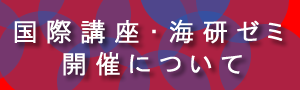自衛隊も出動~国政事案化するクマによる人的被害
2025年11月
遠藤 哲也
遠藤 哲也
この所、ほぼ連日のようにクマによる人的被害が報じられています。2025年度のクマによる死亡事案は13人、人身被害の総件数は8月時点(9月末更新統計)で109人となっており、過去最多の人的クマ被害を記録した2023年度の死者6名、108人(同月比)を上回っています(但し、総件数としては多いが、この時点では、各道県単位で見た場合の人的被害件数は例年と顕著には違わない)。2025年度のクマ出没件数では8月までで既に1万6千213件と記録上の過去最多となっています(2023年度は1万705件)。一連の事案は危機管理問題であるとともに、広く見れば市民社会と武器の関係を考えるという点で、安全保障社会学の対象でもあるので私も注視しています。
10月末には事案件数最多の秋田県の知事の要請に基づいて自衛隊の出動が決定されました。「文春オンライン」によると1960年代には複数回、自衛隊がクマ駆除を実施した例があるようですし、漁民の要望で、トドの集まる岩礁に銃撃を加えたとの話もありますが(国会の会議録に「射撃訓練によるトドの駆除」が記されている)、現在では自衛隊による害獣駆除には政府は否定的なようで、秋田県に出動する自衛隊は後方支援に当たるようです。かつてのM1ガーランドや64式小銃時代とは異なり、現在の自衛隊が用いる自動小銃弾の5.56㎜小口径高速弾では大型動物への阻止力は不十分、かつ貫通による二次被害リスクが、より大きいと見るのが一般的であり、銃を持っているから駆除ができるとはならないのですが(不向きなのであって、不可能なわけではない)、箱罠の設置・見回りや駆除したクマの輸送は自衛隊でなければできないのかという非代替性に関する疑問は、以前からある養鶏場の殺処分への自衛隊利用同様に問われる所かもしれません。なお、日本の一般警官が持つ拳銃の38スペシャル弾もクマへの制止力は期待し難いものです(海外での、拳銃でクマを倒した事例では多くで357マグナム以上の弾が用いられている)。
2023年のクマ被害多発を受けたものか、今年4月には鳥獣保護法(狩猟法)が改正され、「緊急銃猟」が制度化されました。従来の「有害鳥獣駆除」は山林内に居るクマに対して、ハンターを募って実施しており、市街地に現れたクマを駆除する場合には警察官職務執行法に基づいて警察がハンターに駆除を託すのが基本だったようですが、これはクマが市街地に現れて畑や果樹を荒らして居座っているという程度では発し難いものでした。緊急銃猟は「人の日常生活圏に侵入しているか、侵入するおそれが大きい」、「人命または身体への危害防止のため緊急対応が必要」、「銃猟以外の方法で的確・迅速な対処が困難」、「住民・第三者に銃による危害を及ぼすおそれがない」の四条件の成立を前提に自治体首長が発砲指示を出せるというものです。
当初、この制度には、却って従来より迂遠な手続きが必要となるのではないかという否定的見解も見られました。例えば、新狩猟法が施行される直前の今年7月18日に北海道の福島町で男性1人を殺害したと見られるクマが住宅裏の茂みで駆除されましたが、映像で現場地域を見る限り住宅地であり、午前3時半という時間もあって、緊急銃猟としての住民避難などの条件が付されていたら実施できなかった事例かもしれません。一方で、2018年に北海道砂川市役所から依頼を受けた猟友会員が、市職員と警察官が同行のもとでクマを射殺した件で、後日、発砲方向の土手の上方に住宅があったとして猟銃所持許可が取消処分となった事案の影響で、ハンター達が駆除要請の引き受けを渋るようになっていた状況においては、以前より責任関係が明確となったとの肯定評価もあります。
緊急銃猟の難点は「安全確保が可能な場所での発砲」という条件にあります。環境省の緊急銃猟ガイドライン (P30)では「住居や広場、生活用道路、商業施設、農地その他の勤務地、電車、自動車、船舶等も含まれ…住居集合地域等も、人の日常生活圏に含まれる」とされ、緊急銃猟の範囲とされています。しかし、寒村ではなく、都市部の住宅密集地で、ガイドラインの「事例」に示されているような半径200m以内の住民避難というのは、法的に「警戒区域」を設定して行う自衛隊の不発弾の現地処理並みの状況であり、実施困難な手続きに思えます。また、弾丸が跳弾せずに止まる土の「バックストップ」の確保も場所によっては困難な条件でしょう。屋内での発砲についても後方となる壁の材質が弾丸を貫通させない事、貫通する場合はその先にバックストップがあるべき事を述べていますが、材質確認の困難さや、一般住宅の壁がライフル弾を阻止できないであろう事を考えると、都市部住宅地や屋内での緊急銃猟は、よほどの切迫性がない限り、実質的には無理筋だと見なされる事になりそうな気がします。
とは言え、法施行以降10月だけで10件の緊急銃猟による発砲が行われました。個々の事案ごとの環境条件を確認できていませんが、報道映像で確認できた事案では「住宅地」と報じられても、家々が間遠で、隣接して林があるような場所で、木々の間に潜んだ所を撃っており、隣家が立ち並ぶ都市型住宅街という環境ではないように見受けました(新潟県阿賀野市で行われた建物内での緊急銃猟は麻酔銃を用いています。麻酔は効果が出るまでに暴れる恐れがあるため避けられるのですが、体躯の小さな子熊だったため実施したのかもしれません)。
従来、人を避けるものと見なされてきたクマがなぜ、人里に頻繁に現れ、人間の存在や機械音などを気にせず道路を闊歩したり、市街地に留まったり、積極的に人を襲ったり、車に体当たりしてきたりする事が同時多発的に広い範囲で見られるようになったのかは現在の疑問です。ドングリは周期的に豊作・不作を繰り返すため不作は頻繁に起こる事ですし、全国一律でもありません。夏の暑さを言う人がいますが、昨年は猛暑でしたがドングリは概ね豊作でした。今年も肥え太ったクマの目撃例もあります。全国的に深刻化しているシカの食害による森林の劣化が、ツキノワグマの人里出没に影響する事を示唆する研究も出ていますし、メガソーラーによる森林破壊の影響なども含め、多くの可能性を検討する必要があるでしょう。
また、全体としてクマの個体数が増加傾向にあるのは事実のようです。日本の自然界の頂点にいるクマは、人間が狩らねば飢餓か病気くらいでしか減少しませんが、山林内にエサが減少しても、人里付近で食料を確保する事で、幼獣が餓死しなくなっているのかもしれません。山村の人口は減り、山麓の田畑や果樹は放棄され、放し飼いの犬も居なくなった結果、クマが人の生活圏に入り込み易くなっていると言われます。
いずれにせよ、これだけ出没数が増大し、クマが人を襲う事が顕著に見られる段階に至っては、ほとんどが趣味で狩猟をしているハンターに1万円前後程度と思われる日当で身体的・法的リスクを負わせ続けるのは難しいでしょう。米国では魚類野生生物局がヘリからの射撃まで用いてイノシシ駆除を行っていますが、日本では平素は通常の任務に携わり、事案発生の時に呼集出動するパートタイム型のチームを機動隊内など警察内に編成するのが現実的なのかもしれません。
追記:10月30日、クマ対策が初めて閣議で扱われる事となり、木原官房長官は、クマ猟の知識とスキルを身につけた警官を確保し、ライフルによる駆除の実施の検討を警察庁に指示したと公表しました。機動隊員によるライフル狩猟も検討されはじめたようです。70年代以降、民間依存だった日本の獣害対策は新たな展開を見せるのかもしれません。一方、官が駆除に加わるようになる事で逆に、地域的伝統も伴う民間の狩猟文化が衰退するような新たな狩猟規制ができない事も願う所です。
10月末には事案件数最多の秋田県の知事の要請に基づいて自衛隊の出動が決定されました。「文春オンライン」によると1960年代には複数回、自衛隊がクマ駆除を実施した例があるようですし、漁民の要望で、トドの集まる岩礁に銃撃を加えたとの話もありますが(国会の会議録に「射撃訓練によるトドの駆除」が記されている)、現在では自衛隊による害獣駆除には政府は否定的なようで、秋田県に出動する自衛隊は後方支援に当たるようです。かつてのM1ガーランドや64式小銃時代とは異なり、現在の自衛隊が用いる自動小銃弾の5.56㎜小口径高速弾では大型動物への阻止力は不十分、かつ貫通による二次被害リスクが、より大きいと見るのが一般的であり、銃を持っているから駆除ができるとはならないのですが(不向きなのであって、不可能なわけではない)、箱罠の設置・見回りや駆除したクマの輸送は自衛隊でなければできないのかという非代替性に関する疑問は、以前からある養鶏場の殺処分への自衛隊利用同様に問われる所かもしれません。なお、日本の一般警官が持つ拳銃の38スペシャル弾もクマへの制止力は期待し難いものです(海外での、拳銃でクマを倒した事例では多くで357マグナム以上の弾が用いられている)。
2023年のクマ被害多発を受けたものか、今年4月には鳥獣保護法(狩猟法)が改正され、「緊急銃猟」が制度化されました。従来の「有害鳥獣駆除」は山林内に居るクマに対して、ハンターを募って実施しており、市街地に現れたクマを駆除する場合には警察官職務執行法に基づいて警察がハンターに駆除を託すのが基本だったようですが、これはクマが市街地に現れて畑や果樹を荒らして居座っているという程度では発し難いものでした。緊急銃猟は「人の日常生活圏に侵入しているか、侵入するおそれが大きい」、「人命または身体への危害防止のため緊急対応が必要」、「銃猟以外の方法で的確・迅速な対処が困難」、「住民・第三者に銃による危害を及ぼすおそれがない」の四条件の成立を前提に自治体首長が発砲指示を出せるというものです。
当初、この制度には、却って従来より迂遠な手続きが必要となるのではないかという否定的見解も見られました。例えば、新狩猟法が施行される直前の今年7月18日に北海道の福島町で男性1人を殺害したと見られるクマが住宅裏の茂みで駆除されましたが、映像で現場地域を見る限り住宅地であり、午前3時半という時間もあって、緊急銃猟としての住民避難などの条件が付されていたら実施できなかった事例かもしれません。一方で、2018年に北海道砂川市役所から依頼を受けた猟友会員が、市職員と警察官が同行のもとでクマを射殺した件で、後日、発砲方向の土手の上方に住宅があったとして猟銃所持許可が取消処分となった事案の影響で、ハンター達が駆除要請の引き受けを渋るようになっていた状況においては、以前より責任関係が明確となったとの肯定評価もあります。
緊急銃猟の難点は「安全確保が可能な場所での発砲」という条件にあります。環境省の緊急銃猟ガイドライン (P30)では「住居や広場、生活用道路、商業施設、農地その他の勤務地、電車、自動車、船舶等も含まれ…住居集合地域等も、人の日常生活圏に含まれる」とされ、緊急銃猟の範囲とされています。しかし、寒村ではなく、都市部の住宅密集地で、ガイドラインの「事例」に示されているような半径200m以内の住民避難というのは、法的に「警戒区域」を設定して行う自衛隊の不発弾の現地処理並みの状況であり、実施困難な手続きに思えます。また、弾丸が跳弾せずに止まる土の「バックストップ」の確保も場所によっては困難な条件でしょう。屋内での発砲についても後方となる壁の材質が弾丸を貫通させない事、貫通する場合はその先にバックストップがあるべき事を述べていますが、材質確認の困難さや、一般住宅の壁がライフル弾を阻止できないであろう事を考えると、都市部住宅地や屋内での緊急銃猟は、よほどの切迫性がない限り、実質的には無理筋だと見なされる事になりそうな気がします。
とは言え、法施行以降10月だけで10件の緊急銃猟による発砲が行われました。個々の事案ごとの環境条件を確認できていませんが、報道映像で確認できた事案では「住宅地」と報じられても、家々が間遠で、隣接して林があるような場所で、木々の間に潜んだ所を撃っており、隣家が立ち並ぶ都市型住宅街という環境ではないように見受けました(新潟県阿賀野市で行われた建物内での緊急銃猟は麻酔銃を用いています。麻酔は効果が出るまでに暴れる恐れがあるため避けられるのですが、体躯の小さな子熊だったため実施したのかもしれません)。
従来、人を避けるものと見なされてきたクマがなぜ、人里に頻繁に現れ、人間の存在や機械音などを気にせず道路を闊歩したり、市街地に留まったり、積極的に人を襲ったり、車に体当たりしてきたりする事が同時多発的に広い範囲で見られるようになったのかは現在の疑問です。ドングリは周期的に豊作・不作を繰り返すため不作は頻繁に起こる事ですし、全国一律でもありません。夏の暑さを言う人がいますが、昨年は猛暑でしたがドングリは概ね豊作でした。今年も肥え太ったクマの目撃例もあります。全国的に深刻化しているシカの食害による森林の劣化が、ツキノワグマの人里出没に影響する事を示唆する研究も出ていますし、メガソーラーによる森林破壊の影響なども含め、多くの可能性を検討する必要があるでしょう。
また、全体としてクマの個体数が増加傾向にあるのは事実のようです。日本の自然界の頂点にいるクマは、人間が狩らねば飢餓か病気くらいでしか減少しませんが、山林内にエサが減少しても、人里付近で食料を確保する事で、幼獣が餓死しなくなっているのかもしれません。山村の人口は減り、山麓の田畑や果樹は放棄され、放し飼いの犬も居なくなった結果、クマが人の生活圏に入り込み易くなっていると言われます。
いずれにせよ、これだけ出没数が増大し、クマが人を襲う事が顕著に見られる段階に至っては、ほとんどが趣味で狩猟をしているハンターに1万円前後程度と思われる日当で身体的・法的リスクを負わせ続けるのは難しいでしょう。米国では魚類野生生物局がヘリからの射撃まで用いてイノシシ駆除を行っていますが、日本では平素は通常の任務に携わり、事案発生の時に呼集出動するパートタイム型のチームを機動隊内など警察内に編成するのが現実的なのかもしれません。
追記:10月30日、クマ対策が初めて閣議で扱われる事となり、木原官房長官は、クマ猟の知識とスキルを身につけた警官を確保し、ライフルによる駆除の実施の検討を警察庁に指示したと公表しました。機動隊員によるライフル狩猟も検討されはじめたようです。70年代以降、民間依存だった日本の獣害対策は新たな展開を見せるのかもしれません。一方、官が駆除に加わるようになる事で逆に、地域的伝統も伴う民間の狩猟文化が衰退するような新たな狩猟規制ができない事も願う所です。