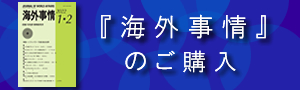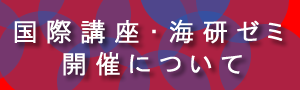日本産水産物の輸入解禁
2025年7月
富坂 聡
富坂 聡
中国、日本産水産物の輸入を即時に再開すると発表――。
6月30日、日本のメディアは一斉にこう報じました。
この問題ではいくつかのメディアからの問い合わせもありました。私の答えは簡潔です。当然の流れ、だからです。
中国はこのところ対日政策を「小さな対立点を除き、日本に融和的な態度で臨む」という方向に向けてきていました。私はこれを中国版「スモールヤード・ハイフェンス」と呼び、さまざまな媒体で発表してきました。
今回の措置もその一環です。
日本水産物の輸入禁止は、2023年8月、日本が福島原発から流れ出た処理水を海洋放出したことに中国が反発して始まりました。中国はこれを汚染水と呼び、たとえ水で薄めても生態系への影響は不可避と反発しました。
ただ、事の経緯を見ていて思ったのは、中国は日本がアメリカの了解だけを取り付け、中国の頭越しに放出を決めたことにへそを曲げたのではないかということです。
当時、私は出演したテレビ番組で「日本側に自信があるのなら、中国を招いて独自に検査させれば良い」と発言し、ネットでたっぷり叩かれました。
だが、どうでしょう。輸入再開に際し外交部は「今年に入ってから、福島原発汚染水海洋放出の国際モニタリングが継続的に行われ、中国側の独自サンプリング検査の結果に異常がなかったことを踏まえ」と説明しています。
つまり日本政府も最終的には中国に調査させ輸入再開にこぎつけたのです。
残念なことは、日本政府が最初から無責任な世論と距離を置き、さっさと中国に検査させていれば約2年間の損失は避けられたのではないかということです。
今年、日中交流の場で交わされた政治の話題もたいていは水産物の輸入再開問題でした。
1月の第9回日中与党交流協議会。3月の第6回日中ハイレベル経済対話も同じです。
もし最初から中国を巻き込んで進めていれば、時間のロスは防ぐことができ、別の問題を話し合う機会に充てられたのです。やはり対外政策に大衆の熱狂は無用です。
実際、日本の損失は時間だけにとどまりません。日本産海産物が中国でブランドであることに変わりはませんが、この間、大量にベトナム産も入り込み、日本の穴を埋めてきました。
中国産もそうです。すでに35年連続で水産物総生産量で世界一を続けている中国ですが、昨今は質の向上も顕著です。養殖技術も日進月歩。それを考えると政治的対立で生まれる空白はライバルを助ける愚かな行為でしかないのです。
6月30日、日本のメディアは一斉にこう報じました。
この問題ではいくつかのメディアからの問い合わせもありました。私の答えは簡潔です。当然の流れ、だからです。
中国はこのところ対日政策を「小さな対立点を除き、日本に融和的な態度で臨む」という方向に向けてきていました。私はこれを中国版「スモールヤード・ハイフェンス」と呼び、さまざまな媒体で発表してきました。
今回の措置もその一環です。
日本水産物の輸入禁止は、2023年8月、日本が福島原発から流れ出た処理水を海洋放出したことに中国が反発して始まりました。中国はこれを汚染水と呼び、たとえ水で薄めても生態系への影響は不可避と反発しました。
ただ、事の経緯を見ていて思ったのは、中国は日本がアメリカの了解だけを取り付け、中国の頭越しに放出を決めたことにへそを曲げたのではないかということです。
当時、私は出演したテレビ番組で「日本側に自信があるのなら、中国を招いて独自に検査させれば良い」と発言し、ネットでたっぷり叩かれました。
だが、どうでしょう。輸入再開に際し外交部は「今年に入ってから、福島原発汚染水海洋放出の国際モニタリングが継続的に行われ、中国側の独自サンプリング検査の結果に異常がなかったことを踏まえ」と説明しています。
つまり日本政府も最終的には中国に調査させ輸入再開にこぎつけたのです。
残念なことは、日本政府が最初から無責任な世論と距離を置き、さっさと中国に検査させていれば約2年間の損失は避けられたのではないかということです。
今年、日中交流の場で交わされた政治の話題もたいていは水産物の輸入再開問題でした。
1月の第9回日中与党交流協議会。3月の第6回日中ハイレベル経済対話も同じです。
もし最初から中国を巻き込んで進めていれば、時間のロスは防ぐことができ、別の問題を話し合う機会に充てられたのです。やはり対外政策に大衆の熱狂は無用です。
実際、日本の損失は時間だけにとどまりません。日本産海産物が中国でブランドであることに変わりはませんが、この間、大量にベトナム産も入り込み、日本の穴を埋めてきました。
中国産もそうです。すでに35年連続で水産物総生産量で世界一を続けている中国ですが、昨今は質の向上も顕著です。養殖技術も日進月歩。それを考えると政治的対立で生まれる空白はライバルを助ける愚かな行為でしかないのです。